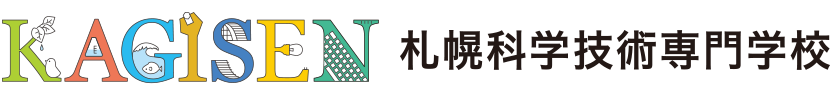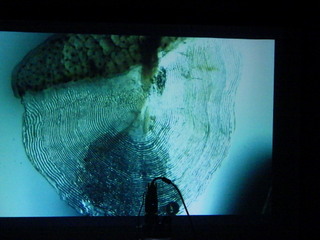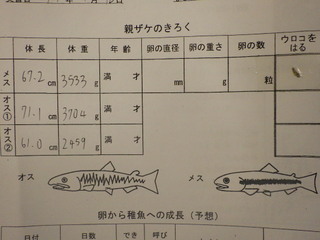サケの人工授精
カレーは飲み物、と言った芸能人がいましたが、
米は飲み物です。
念のため、ご飯ではなく加工品ですのであしからず。
お元気ですか。海洋生物学科の岡本です。
さて、1年生は先日、札幌市豊平川さけ科学館に行ってきました。
北海道の水産業・栽培漁業でサケははずせまんので、
必須実習といっても過言ではありません。
まずは、親魚をタモ網ですくいます。
続いて、馴れてない人には衝撃の作業。
棍棒で叩いてサケを気絶させます。
K越くんは優しい性格なのか、なかなか気絶させられません。
選手交代。
本職登場です。
M浦くんは恐らく、実家の仕事の関係から、
サケを叩くのは馴れているのかと。
秒で仕留めていました。
メスは大切な採卵を控えていますので、
麻酔にかけて眠らせます。
大人しくなったオスとメスを運びます。
オスとメスの違いなどを教えていただきます。
雌雄差は、吻端の形状だけではないようで、勉強になります。

|

|
尾叉長と体重を測定します。
魚の長さって、体長だの尾叉長だの、色々ありますね。
学校で、魚のパーツの名前は頑張って覚えましょう。
いよいよ、採卵。

|

|
鮮やかな卵がこぼれ出てきます。
続いて、精子を採精します。
インターンシップで体験済みのY永くんは、手際よく豪快に採精しています。
鳥の羽で優しく混合します。
ここではまだ、受精していません。
水に出会わないと受精しないのです。
逆に、タイミング悪く水が存在してもいけないので、気を使うところです。
受精の瞬間。
ここから命が始まります。
お役御免。
ではありません。
まだまだ、学ばせてもらいます。
ピンセットで鱗を抜いているところ。
サケの鱗は年齢査定に使われます。
餌の少ない冬は、年輪の幅が狭い冬期帯と呼ばれる筋になります。
このサケは3歳魚でした。
測定結果を記録しておきます。
最後に、
解剖をしていただきました。
消化器官や耳石など、色々な場所を解説していただき、
学生からの素朴で鋭い質問なども出て、
とても有意義な実習になったと思います。
純粋に、魚のことに疑問を持ったり、詳しくなったりするのは、
普段の授業と変わらないのですが、
やっぱり校外で、実際の魚に触れると知的好奇心が湧くのでしょうか。
岡本も見習わなければなりません。