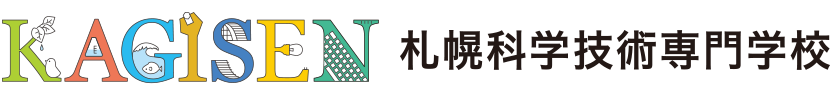細菌の顕微鏡観察技術、上達しました
グラム染色や鞭毛染色を行い
顕微鏡で細菌を観察してきましたが
細菌観察の最後は、“芽胞染色”です。

好気性の芽胞形成菌である
枯草菌(Bacillus subtilis)を染色・観察しました。

「試験菌を塗沫する」と説明するだけで
何を使って、何を、どう火炎滅菌かも手慣れたものです。

今回は、1枚のスライドグラスに
培養時間が長いものと短いものと2か所に広げました。
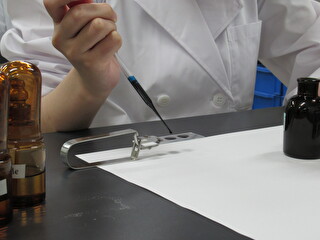
熱や乾燥に強い“芽胞”は
薬品にも耐性があるので加温染色を行います。
栄養細胞を対比染色して、水洗、乾燥、検鏡です。
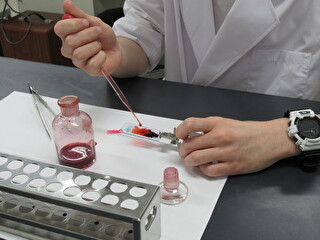
試験菌を取りすぎると・・・
枯草菌で視野が真っ赤になっていますが
青く染まった芽胞が見えます。
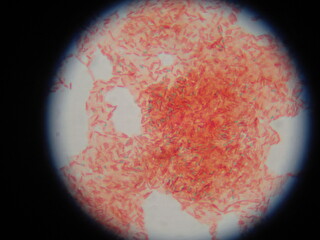
(上の画像を拡大したものです)
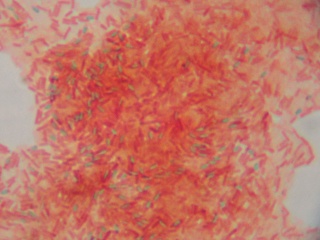
ですが、試験菌がまばらな所を探せば
枯草菌自体の形態(桿状)もわかります。
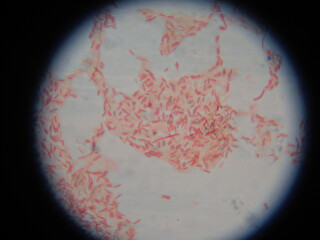
(上の画像を拡大したものです)
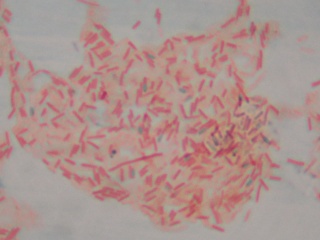
培養時間が短いと、栄養細胞が多く観察され
長いと芽胞が多く観察されます。
始めて顕微鏡で細菌を観察しても
「見えない」、「わからない」だった頃からひと月ほどが経ち
今では100倍の対物レンズにもすっかり慣れました。
夏休み明けからは、真菌類の観察に入ります!